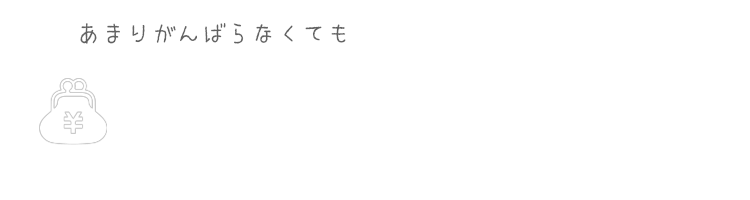こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。
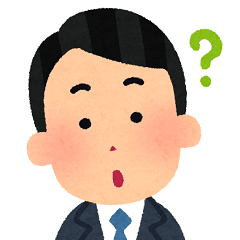
ここはどんなブログなの?
- お金、投資、資産運用、副業が中心のブログです。
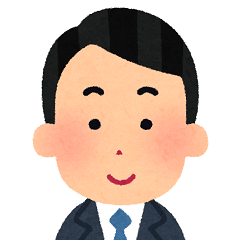
この記事を書いたそーたろーはこんな人です。
- 2008年から国内・海外ETF、つみたてNISA、iDeCoなどでインデックス投資をしています。
- 2020年より米国株オプション、サラリーマン大家、副業ブログを実験中です。
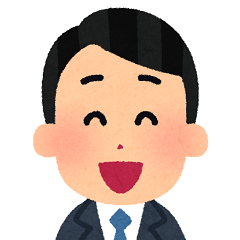
この記事は次のような人にオススメです
- 「選択制」確定拠出年金の損得が知りたい人
- 「選択制」確定拠出年金の損得を自分で計算したい人
この記事の目的

老後資金の準備という観点から資産運用としてiDeCo(個人型DC)、つみたてNISAが普及してきています。
同じように確定拠出年金制度の一形態である企業型DCを導入する会社も増えています。
こうした状況の背景としては、国や会社が個人の福利厚生の面倒を見るシステムが立ち行かなくなってきていることがあげられるでしょう。
公的な制度による特典を設けることで自助努力による資産形成を促すことが目的です。
企業型DCについてはいくつかのパターンがありますが、加入者(社員)が自由に選択できるわけではありません。
今回紹介する企業型DCのひとつ「選択制」確定拠出年金もクセのある制度で、加入者が一方的に割を食う部分があります。
「選択制」確定拠出年金に加入する上で知っておくべき注意点や考え方、ご自身のケースでの概算の求め方を紹介します。
- 選択制DCに加入すべきかどうかは各個人の置かれた状況と考え方によります
- メリットは社会保険料が安くなる、節税になる、受取時に退職所得控除が使えるなど
- デメリットは厚生年金が減る、資金拠出が給与型の場合は各種給付金が減るなど
- 損得の計算についてはこの記事の終盤で紹介する方法でメリットとデメリットを算出して、ご自身のケースに当てはめて評価する必要があり非常に煩雑です
【結論】「選択制」確定拠出年金には加入すべき?

最初に私が考える加入した方がよい人・しない方がいい人を以下の3パターン紹介します。
加入した方がよい人
積極的にリスクが取れる人は加入した方がよいでしょう。
「選択制」確定拠出年金の加入によって縮小する社会保障は預貯金でカバーし、掛け金はリスク資産に投じて老後資金に備えるのがよいでしょう。
段階的に加入した方がよい人
家計の状況などの理由でリスクを取りたいが取りにくい人はリスクヘッジも検討しながら部分的・段階的に加入するのがよいでしょう。
特に社会保障縮小の影響が大きい人は民間保険に加入して万が一に備える対応が考えられます。
加入しない方がいい人
リスクが取れない人は加入しない方がよいでしょう。
特に経済状況が思わしくない人の場合、DCの掛け金は途中の取り崩しができないため将来の心配よりも目先の生活の方が大切でしょう。
収入と支出を見直して貯金ができるようになってからでも間に合うでしょう。
「選択制」確定拠出年金のメリット・デメリット

「選択制」確定拠出年金の全体としてのメリットとデメリットは以下のとおりです。
デメリットをまとめると以下のとおりです。
|
項目
|
資金拠出の方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 給与型 | 賞与型 | |||
|
社会保険
|
介護保険料 | 影響なし | 影響なし | |
|
健康保険料
|
健康保険 | 影響なし | 影響なし | |
| 出産育児一時金 | 影響なし | 影響なし | ||
| 出産手当金 | 減額3 | 影響なし | ||
| 傷病手当金 | 減額3 | 影響なし | ||
|
雇用保険料
|
失業給付金 | 減額3 | 影響なし | |
| 育児休業給付金 | 減額3 | 影響なし | ||
| 介護休業給付金 | 減額3 | 影響なし | ||
|
厚生年金保険料
|
老齢厚生年金 | 減額1 | ||
| 障害厚生年金 | 減額2 | |||
| 遺族厚生年金 | 減額2 | |||
| 労働災害の休業補償給付 | 減額2 | 影響なし | ||
影響の受け方をまとめると以下のとおりです。
タイプ別に減額1〜3にわけて考えた場合の各ポイントは以下のとおりです。
これらのデメリットの影響度とメリットを比較して評価します。
企業型DCと「選択制」確定拠出年金

確定拠出年金制度について簡単におさらいします。
確定拠出年金制度の概要については以下も参考にしてください。

企業型DCの特徴
企業型DCでは掛け金を従業員それぞれが運用します。
掛け金は給与のように社会保険料や税金の対象とならないので有利に資産形成ができます。
運用商品の選び方については以下の記事もどうぞ。

「選択制」ではない確定拠出年金とは?
会社が掛け金を拠出する方式で、体力のある大きな会社が導入します。
いくつかある企業型確定拠出年金の形態のひとつです。
「選択制」確定拠出年金とは?
こちらも企業型確定拠出年金の形態のひとつで、この記事のテーマです。
主に掛け金を出せない中小企業が導入し、加入者(社員)が自分の給与の中から確定拠出年金の掛金を拠出します。
財形貯蓄が近いイメージです。
給与の一部を今受け取るか将来に回すかを自分で選択することができます。
掛け金は給与から控除されるので給与として受け取る額面が減ることになります。
「選択制」確定拠出年金の掛け金のイメージは以下のとおりです。
掛け金は上限55,000円までの範囲で自分の好きな金額を指定することができ、その分だけ給与から控除されます。
「選択制」確定拠出年金の特徴をまとめると以下のとおりです。
これだけを見てやった方がよいのか、やらない方がよいのかよくわからないのも「選択制」確定拠出年金の特徴です。
「選択制」確定拠出年金の問題点
まず「選択制」確定拠出年金の掛け金は給与ではなくなるため年収が減ります。
会社から支払われるお金は従来どおりですが掛け金は収入として扱われません。
つまり会社員の収入の証である源泉徴収票に計上されないので、見かけ上の年収が下がります。
見過ごされがちですがかなりのデメリットになり得ます。
次に「選択制」確定拠出年金の社会保険料を減らして節約する考え方とその効果がわかりにくいです。
最後に「選択制」確定拠出年金では掛け金の拠出を毎月の給料から拠出する方式と賞与から拠出する方式があります。
給与型の場合はメリット・デメリットの把握がとても困難です。
実際の損得についてはほとんどの加入者がわかっていないのが実情と推測します。
【重要】資金拠出における給与型の欠点
「選択制」確定拠出年金の資金拠出の方法と影響は以下のとおりです。
給与か賞与かというタイミングの問題だけならどっちでもいいような気がします。
しかし給与型と賞与型では標準報酬月額への影響の有無が変わってしまうため、給与型の方が一方的に不利になるという欠点があり、回避策は提供されていません。
社会保障や老齢年金は、給与所得に応じて標準報酬月額の等級が決まり、社会保険料を払った額によって受けられる保障や年金額が変わります。
つまり給与型で毎月資金拠出すると掛け金が給与所得から控除されるため標準報酬月額の等級が下がります。
その結果、最初の表のとおり社会保障の一部の給付金の減額が起こります。
だったら賞与型で拠出すればいいじゃん、って思うでしょう?
それができないんです。なぜなら、
つまり会社が「ウチは給与型です」って決めたら従業員は従うしかありません。
さらに加入者にとって都合が悪いことに、賞与型は給与型にくらべ会社の運営コストが余計に掛かるという背景があります。
賞与型では社員の途中退職に備えて掛け金の前払いか、プールをするなどの対応が必要です。
人件費を削りたいのに、社員のためを思ってそんな面倒な運用を採用する会社は少ないでしょう。
すでに給与型の資金拠出で「選択制」確定拠出年金が始まっている場合、賞与型に変更するならば従業員側から意見を提出して従業員規則の改定という大掛かりな話になります。
しかしこうした制度上の欠点は意図的に作られたものであると考えるべきでしょう。
要するに目的は社会保障費の削減で、いわゆるアメとムチの施策ということです。
つまり知らなければ搾り取られるだけだし、社会情勢をかんがみれば会社やお上に文句を言っても仕方ないということです。
我々大衆にできるのは与えられたアメをどうやったら上手に利用できるか考えることではないでしょうか。
というわけで、以降ではこうした欠点のある「選択制」確定拠出年金の影響度を検証します。
メリットとデメリットの比較

サンプルケースを使って実際の数字を概算で算出してみました。
サンプルケースの基本条件は以下としました。
なお以下の点に注意してください。
今回は掛け金2万円/月のたとえ話です。
メリットまとめ
|
項目
|
「選択制」確定拠出年金 | ||
|---|---|---|---|
| なし | あり | 差額 | |
| 社会保険料の総額 | 17,863,200円 | 16,488,000円 | 1,375,200円 |
| 所得税、住民税の総額 | 7,560,000円 | 6,885,000円 | 675,000円 |
| 掛け金 | – | 7,200,000円 | 7,200,000円 |
| 運用益(3%) | – | 4,450,000円 | 4,450,000円 |
| 運用益(5%) | – | 9,440,000円 | 9,440,000円 |
節約できる金額
掛け金と運用益
今回の受け取りは「一時金」で一括とし、税金の計算式については以下のとおりです。
- 退職所得控除(30年):800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
- 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
- 所得税率:195万円以下は5%
- 住民税率:10%
これらのメリットが以降のデメリットと見合うかを考えます。
デメリットまとめ
|
タイプ
|
項目
|
「選択制」確定拠出年金 |
補足
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| なし/ あり(賞与型) |
あり (給与型) |
差額 | |||
| 減額1 | 老齢厚生年金 | 591,948円 | 552,484円 | -39,463円 | 30年加入時の年額 |
|
減額2
|
遺族厚生年金 | 443,961円 | 414,363円 | -29,598円 | 30年加入時の年額 |
| 障害厚生年金(1級) | 739,935円 | 690,605円 | -49,330円 | 30年加入時の年額 | |
| 障害厚生年金(2・3級) | 591,948円 | 552,484円 | -39,463円 | 30年加入時の年額 | |
| 労働災害の休業補償給付 | 567,327円 | 522,000円 | -45,327円 | 休業期間90日の場合 | |
|
減額3
|
出産手当金 | 566,146円 | 522,536円 | -43,610円 | 支給98日の場合 |
| 傷病手当金 | 3,148,465円 | 2,905,940円 | -242,525円 | 支給1年6ヶ月の場合 | |
| 失業給付金 | 498,960円 | 477,810円 | -21,150円 | 支給3ヶ月の場合 | |
| 育児休業給付金 | 1,755,000円 | 1,614,600円 | -140,400円 | 支給1年の場合 | |
| 介護休業給付金 | 502,500円 | 462,300円 | -40,200円 | 支給3ヶ月の場合 | |
【評価】計算結果から比較検討
減額1について
老齢厚生年金についてはメリットが上回るのではないか、というのが私の考えです。
30年加入して、20年受給した場合はメリットが上回ります。
年金はこれに加えてDCの影響を受けない1階部分の基礎年金があります。
さらに掛け金+運用益も加味すると老後資金という点では問題ないように思います。
減額2について
遺族年金、障害年金
万が一のための社会保障が縮小します。
しかし2階部分の厚生年金、額にしてー3〜5万円/年の縮小です。
以下のような点も加味して影響度を考えるべきでしょう。
また今回のサンプルケースは30年加入した想定ですが、遺族年金、障害年金は現役世代の万が一をカバーする目的があります。
加入期間がより短いケースではそもそも受給額が少ないのに、さらに選択制DCで縮小することは認識しておくべきでしょう。
労働災害の休業補償給付
こちらはもともとの補償額が大きい(賃金×80%)のでサンプルケース90日の給付でも大きめの額の差が付きます。
遺族年金、障害年金と同様に突発的なアクシデントへの備えです。
以下の重要度が高い場合にはあまり削るべきではないでしょう。
減額3について
「選択制」確定拠出年金で資金拠出が給与型の場合に各種給付金が減額になります。
特に傷病手当金は加入者全員に関係し、万が一のための社会保障が縮小します。
給付金は使う人・使わない人、使う回数が変わるので影響度は人によって異なるでしょう。
【参考】そーたろーの個人的な意見
制度の実態としては資金拠出が給与型になるケースが多いと思われ、以下がポイントになると考えています。
一般化できませんが、以下のようなケースで判断が必要ではないでしょうか。
個人的には、給与型で資金拠出してリスク資産で運用せずに貯蓄だけしても社会保障の縮小デメリットの割に合うかは微妙なところです。
今回の例では30年拠出して20年老齢年金を受給した場合で以下の差額が手元に残る計算です。
単純にこの金額と現役時代の減額2と減額3のデメリットを天秤に掛けた場合、人によってはやらない方が合理的なケースもあるのかなという感触です。
この問題の評価が難しいのは、以下のような点だと思われます。
判断が微妙な場合の解決策としては以下が有力ではないかと考えています。
ここで問われていることは、最終的にはリスクを取れるかどうかという問題に集約されると考えていて、まとめると以下のとおりです。
結局は収入を増やす、支出を減らす、残ったお金を運用するという基本原則に行き着く気がします。

そーたろーのケース
私の勤務先は選択制DCを導入しています。
私は選択制DCに加入済みで、掛け金は100%株式インデックスに振り向けています。
なお企業型DCの加入前はiDeCoに加入していて、選択制DCの加入に際してiDeCoは運用指図者になったのでよかったら参考にしてください。

あと、DCを切り替えるとふるさと納税にも影響がありますね。

【参考】メリットとデメリットの計算方法

今回説明した社会保障への影響については自分で調べることができます。
ご自身のケースを見積もりたい人は以下を参考にしてください。
メリットの計算
社会保険料の減額
所得税、住民税の節税
運用益の計算

退職金の税金
デメリットの計算
出産手当金
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算 | keisan
傷病手当金
失業給付金
育児休業給付金
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算 | keisan
介護休業給付金
労働災害の休業補償の給付金
厚生年金の減額
老齢厚生年金
遺族厚生年金
障害厚生年金
障害1級
障害2、3級
まとめ
今回は「選択制」確定拠出年金の影響とメリット・デメリットを紹介しました。
調べていて思いましたが、今回の論点について自分のケースを調べて各自で判断して適切な選択をするというのは、恐らくほとんどの人にとって不可能でしょう。
社会情勢をかんがみれば仕方のないことはわかっていますが弱者に厳しく、強者に優しい、そんな制度だと思います。
弱肉強食はマネーの世界では当たり前のことですが、自己責任の名のもとにみんなが気づかないうちにこっそりと社会保障を削る、そんな意図を感じました。
格差社会を生き抜くために私たちにできることは、勉強して変化に対応していくことではないでしょうか。