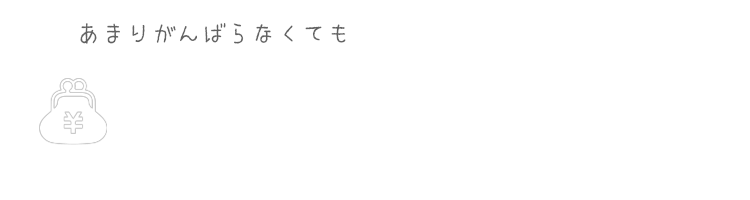こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。
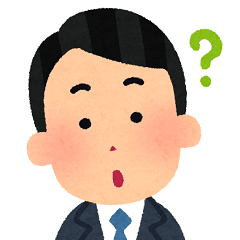
ここはどんなブログなの?
- お金、投資、資産運用、副業が中心のブログです。
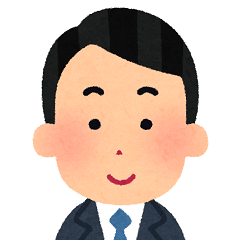
この記事を書いたそーたろーはこんな人です。
- 2008年から国内・海外ETF、つみたてNISA、iDeCoなどでインデックス投資をしています。
- 2020年より米国株オプション、サラリーマン大家、副業ブログを実験中です。
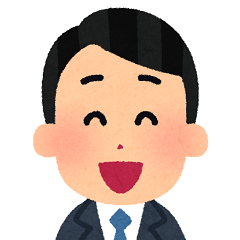
この記事は次のような人にオススメです
- 企業型DCの配分変更、スイッチングに関心がある人
この記事の目的

企業型DCの配分変更とスイッチングを実施したので紹介します。
DC資産の運用変更はあまり頻繁にやるものではないと思われ、私も今回初めて実施しました。
手続きとしては簡単なのですが、なぜそうした変更を行ったか、といった点を紹介できればと思います。
企業型DCの配分変更とスイッチングで定期預金へ

変更の目的
今回の変更の目的は以下の記事で紹介した「冬支度」になります。

2022年現在、世界中でインフレ圧力が増しているため急激な金融引締が行われ、それに伴う景気減速懸念が台頭しています。
この先何がどうなるかは誰もわからないわけですが、私は事前に計画したリスク回避行動を取って備えることにしました。
今回紹介するのはその中の確定拠出年金(DC)で、現在加入者となっている選択制企業型DC部分のお話です。
変更の狙い
先の「冬支度」の記事でも述べていますが、円安株安が進んでいるので一旦利食いして、将来どこかで急激な円高への巻き戻しが起きたときに買い戻せたらスッゴイ儲かるんじゃね、みたいなことを目論んでいます。
相場のことなのでどうなるかはまったくわかりませんが、当たれば利益上乗せ、外しても大損しない範囲で対処したい意向です。
配分変更やスイッチングはDCだけで使える有利な仕組みなので、なにがなんでも「バイ・アンド・ホールド」に固執しなくてもいいんじゃないかと考えています。
この先二度と円高局面が来なければずっと持っていた方がよい事になりますが、タダなんだし折角の機会なので一度くらい使ってみましょうよ。
変更のタイミングについて
2022年9月の最終週に実施しました。
投資格言に「頭と尻尾はくれてやれ」というのがありますが、株安と円安の綱引きを完璧に見切る(天井を言い当てる)ことはできないので、まーなんとなくです。
私はこの先相場は弱含むという見通しを持っていて、急激に円安が進んで先日財務省の為替介入が入ったタイミングであれば、利食い時期としては大きく間違ってはないかな、といった感じです。
ちなみに株価と為替が将来どうなるかを正確に予想することはできませんし、特に長期投資では正確に狙って的中させる必要もなく、値動きを上手に利用できればOK です。
例えば現在為替は145円/ドル近辺で、今がピークかもしれないし、この先160円/ドル、200円/ドルとか行くかもしれませんがピークを当てに行く必要はないです。
もちろん円安のピークで売り抜けて、円高の大底で買い戻せれば大きく儲けられますが、バイ・アンド・ホールドの場合はそもそも為替の上下動を有効活用するような思想がありません。
だから将来200円/ドルになってその後100円/ドルに戻っても落差100円/ドルを捨ててるのと同じです。
つまり円高に備えるなら145円/ドルでも200円/ドルでもタイミングはどこでもいいので円安のうちにいくらかでも利食っておいてそれより円高で買い戻せれば為替差益が取れるという考え方です。
私個人的には2021年末が115円/ドル付近で9ヶ月で145円/ドルで財務省の単独介入ですから、ここらは一旦利食い時かな、って感じです。
実際は株価との綱引きなので株と為替を合成してタイミングを見計らう必要がありますが、あくまでザックリ当てに行く感じでも黙って持っているよりも追加のリターンに寄与できると考えています。

また円高狙いと言ってもそれが20年も30年も先のことだったとしたら機会損失がハンパないので、あくまで数年くらいで機会があればいいなー、くらいの感じです。
なので全資産勝負とかではなく、DC資産に限定すれば配分変更とスイッチングがゼロコストで行えるのでお手軽に遊べるというわけです。
変更手続きについて
手続き的には簡単で、配分変更、スイッチングとも利用しているDCの金融機関にログインしてWEB上で完結できます。
実際の変更は金融機関のWEBサイトへログイン後、JIS&Tが提供する確定拠出年金インターネットサービスで行います。
今回は細かな手順は割愛しますので、不明点がある場合は利用している金融機関にご確認ください。
配分変更
まずは配分変更を実施しました。
配分変更とはDC加入者として拠出設定している資金の振り向け先を変えることを指します。
今回は以下のように変更しました。
この変更により以降は全額が定期預金の買い付けになります。
なお基本的なことですが、DCでは無リスク資産の定期預金に資金拠出して運用益が見込めなくても、拠出金が課税対象とならず節税効果があるので継続する意味があります。
スイッチング
続いて同日にスイッチングも実施しました。
スイッチングとはすでにDC口座で保有している運用商品を別の運用商品へ変更することを指します。
こちらも配分変更と同じく定期預金にしました。
実は今回はとりあえず配分変更だけして、時期をずらして(時間分散して)スイッチングしようと考えていましたが、口座資産を見ていたらパフォーマンスが+11.4%とあまり利益が乗っていなかったので利食いすることにしました。
残るはiDeCo
私はiDeCo口座にも運用指図者として資産を保有していますが、こちらのスイッチングはまた別の機会に実施したいと考えています。
iDeCoの保有資産も外国株式100%で、こちらはパフォーマンスが+60%くらいあってまだまだ下落相場を耐えられそうなので様子見とします。
とは言え2022年の急激な円安と将来円高に巻き戻ったことを想定すると+60%くらいの利益はあっと言う間に吹き飛びそうですね。。。
【余談】DC資産の自動移管が増えている
今年の7月に個人的に以下の調査をしたところ、DCの加入者は企業型、個人型合わせて約1,000万人くらいでした。

DCでは加入資格が変更になったら手続きが必要なのですが、これをやらずに自動移管された人が100万人を超えたというニュースが2022年に入って出ています。
割合としては10%なので相当高いと感じられ、半数以上の口座で残高があるとのことなので世の中のDCに対する関心のなさが表れていると思います。
こうした状況を鑑みるに、マクロ経済を見ながらDCの配分変更やスイッチングを駆使して、自分で判断しながら機動的な対応が取れるというのは、投資手法の良し悪しは別として個人のリテラシーとしてはイイ感じなんじゃないでしょうか、などと思っています。
まとめ
企業型DCの配分変更とスイッチングを実施したので紹介しました。
リスク回避を理由に企業型DCは一旦すべて無リスク資産としました。
★投資デビューはスマホ証券がおすすめ!

★自動運用を始めるなら次世代ロボアドのSUSTENがおすすめ!

★知ってた?インデックス投資×株式オプションで時代を先取り!

★これからインデックス投資を始める方は参考にどうぞ!

★ネット回線は工事不要で即日使えるWiMAXがおすすめ!