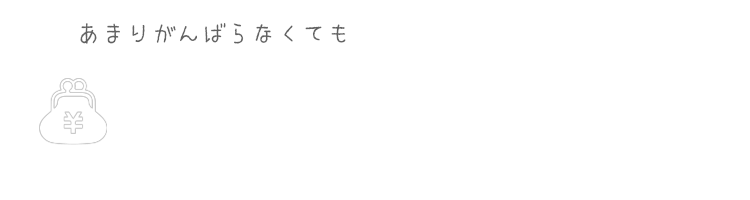こんにちは。『お金に困らない生活(インデックス投資ブログ)』管理人のそーたろー(@sotarowassyoi)です。
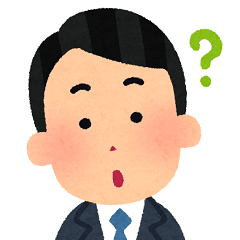
ここはどんなブログなの?
- お金、投資、資産運用、副業が中心のブログです。
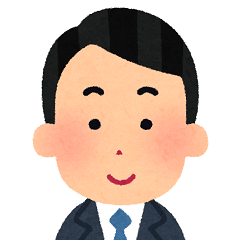
この記事を書いたそーたろーはこんな人です。
- 2008年から国内・海外ETF、つみたてNISA、iDeCoなどでインデックス投資をしています。
- 2020年より米国株オプション、サラリーマン大家、副業ブログを実験中です。
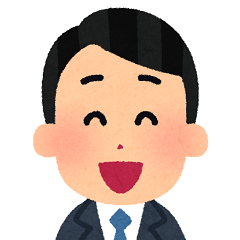
この記事は次のような人にオススメです
- 選択制企業型DCとiDeCoの併用に関心がある人
この記事の目的

選択制企業型DCとiDeCoの併用を紹介します。
選択制企業型DCとiDeCoの併用目的を理解するためにはややマニアックな知識が必要で、かつ併用手続きもそれなりに煩雑です。
ご興味がある方の参考になれば幸いです。

2023年より選択制企業型DCとiDeCoの併用開始
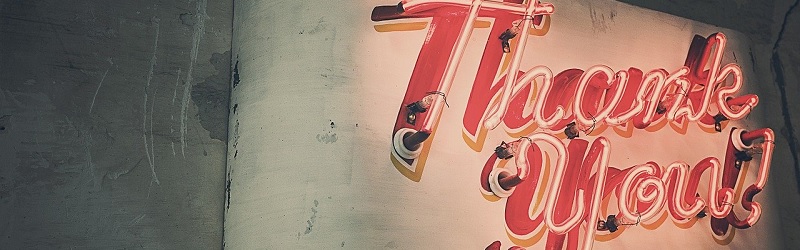
変更前後の資金拠出は以下のとおりです。
併用の目的
併用の目的は、選択制企業型DCのメリット(社会保険料の縮小)を一部手放す代わりにデメリット(社会保険・厚生年金の縮小)を緩和させようというものです。
選択制企業型DC・iDeCOどちらも所得控除の対象ですが、標準報酬月額の変動は選択制企業型DCだけなので、拠出をiDeCoにも振り向けることでメリット・デメリットの影響を和らげることができます。
つまり選択制企業型DCで資金拠出すると標準報酬月額の等級が下がるので、一部をiDeCoに振り向けることで等級を上げようという目論見です。
選択制企業型DCの標準報酬月額の話は非常にビミョーでわかりにくいですね。

一般的な企業型DCと選択制企業型DCの違い
一般的には企業型DCとiDeCoを併用する目的として以下のようなメリット・デメリットが紹介されていることが多いようです。
ところが企業型DCのなかでも選択制企業型DCの場合、従業員が給与の一部を企業型DCの掛金として拠出するため標準報酬月額が下がるので将来の厚生年金が下がったり、現役時代の社会保障がしぼんだり、といったそれなりにインパクトのある別の論点が登場します。
こうした論点はあまり紹介されていないような気がしていて、選択制企業型DCの加入者は自分自身のケースをしっかり見定めて利用する必要がありますね。

併用に関する考察など

併用手続きは煩雑
併用手続きはなかなか難しくて、まず会社に選択制企業型DCの拠出額を下げる申請をして、下げた分をiDeCoで拠出開始する手続きをします。
ただしiDeCoの開始まで時間が開くと機会損失になるし、かといって早すぎると加入期間が重複して還付が発生し還付手数料が発生してしまうので、いい感じになるタイミングを見計らってそれぞれの手続きを申請しなければなりません。
会社のDC担当者、企業型DCのサポート、iDeCoのサポートにそれぞれ確認する必要がありました。

選択制企業型DCの標準報酬月額の問題やiDeCoと併用することのメリット・デメリットはビミョーだし、併用の手続きもそれなりに面倒だし、日本中でこんなことしてるのは私だけなんじゃないかという気がしてきます。
またさらに別の論点として2024年から新NISAが始まることになっていますが、DCは所得控除という強力な特典が付くため、NISAとDCどちらを優先すべきかという課題も持ち上がります。

DCは年金なので資金が拘束される点がポイントで、投資資金がない人はNISA優先、ある人はDC優先というのが一般的な答えになりそうですが、DCという超難解な制度の利用をまず最初に検討しなくてはならないのはかなりハードルが高いと感じます。
ま、制度は難解、判断はビミョー、手続きも複雑で面倒ではありますが、とりあえず使ってみてマズそうならあらためて方向修正ということでいいんじゃないでしょうか。
2023年は併用して、また考えが変わったら2024年以降は選択制企業型DCへの全振りに戻すことを検討したいと思います。
切り替えタイミングはOKっぽい
今回の併用開始については、最大拠出金額(5.5万円/月)で切れ目なく運用できることがひとつの目標でした。
選択制企業型DCは1月の給与分から3.5万円になり、楽天証券のiDeCo2万円拠出は資格取得日が令和5年1月10日で初回引き落とし(1月分)が2月ということで、切り替えタイミングは狙い通りに行ったようです。
iDeCoの開始手続きについては楽天証券の確定拠出年金サポートに問い合わせて、選択制企業型DCの変更適用が1月からなので1月中に実施せよという回答に従いました。
仮に重複による還付が発生しないよう大事を取って、iDecoの手続きを意図的に遅らせた場合の損失は以下のとおりです。
所得税は累進課税なので加入者の課税所得に対応した税率で、DCの最大の特典である節税を手放すことになります。
前回企業型DC開始時に運用指図者になったときは拠出金の重複による高額な還付手数料を徴収されて結構ショックでした。

こうしたことをきちんと段取りしなければならない理由はiDeCo(国民年基金連合会)の手続きに1〜2ヶ月ほど時間がかかり、正確なタイミングが読めないためです。
年金の手続きなのでミスがあっては困るので仕方ないと言えば仕方ありませんが、お役所仕事感は否めませんね。
私はネタ(人柱)としていろいろチャレンジしていますが、多くの人にとってDCは難解なのであまりジタバタしないのが得策だと思います。
併用すべきかは実はビミョー
併用の目的は標準報酬月額を上げるためですが、実はこの選択もツッコミどころがあります。
というのも標準報酬月額を上げると現役時代の社会保障(労災保険とか)が厚くなるメリットはありますが、将来受け取る厚生年金の縮小傾向(支給年齢の引き上げなど)が明らかなことから、併用によって厚生年金を手厚くする今回の施策は悪手であるとも言えます。
したがって併用前の選択制企業型DCに最大掛け金5.5万円/月を拠出する状態(厚生年金が減るのは許容)で社会保険料の支払いを減らした方が合理的かもしれません。
手続き完了後も配分指定で疑問点が
楽天証券とJIS&Tから手続完了の通知が届き、再開にあたってWEB上で掛け金の再配分指定をするように案内されます。
ところが掛け金額20,000円/月のはずが「-」となっていました。
この状態でも配分指定はできているようですが、商品が未指定といった状態に見えました。
一瞬「え、これって別途金額指定の手続きを書面で出すの?」と思ったのですが、確認してみたら再開手続き時の書類で掛け金額を指定しているし、引き落とし金融機関の手続きも済んでいるので反映されていないだけだろうと思い直しました。
しかし黙って待っていて時間だけ過ぎて、何らかのトラブルで再拠出が遅れるのは嫌なので、念のため楽天証券の確定拠出年金サポートへメールで問い合わせました。
その後は回答が来る前(手続き完了通知を受け取ったの翌々日の朝)には掛金額20,000円/月が表示されるようになっており、配分指定も受け付けられていました。
なお楽天証券サポートからの回答によれば、iDeCoの登録データは、毎月中旬頃に更新される仕組みとのことで、このあたりもわかりにくいですね。。。
【参考】2023年はスイッチングを活用中

この記事を書いている2023年初頭時点では私は選択制企業型DC、iDeCo共にいずれも100%定期預金の状態です。


昨今のインフレ、利上げ、ドル高に備えたリスク回避として一時的にキャッシュ化して様子を見ています。
株式ファンドで強気のホールドもいいですが、使えるものはできるだけ有効に使うということでDCのスイッチングは課税なしでリスク調整できて便利なのではと思っています。
諸刃の剣なので機会損失で損したらご愛嬌ですが。。。
まとめ
選択制企業型DCとiDeCoの併用を紹介しました。
選択制企業型DCを利用している方の参考になれば幸いです。
★インデックス投資をしながら米国ETFを使ってお小遣い稼ぎができる!

★既存のインデックス投資にオルタナティブ投資をアドオンできる次世代ロボアド!

★ヘッジやレバレッジでインデックス投資の弱点が補完できる!